Special
PIZZICATO ONEインタビュー~ピチカート・ファイヴの7インチ・ボックス&最新ベスト盤、そして10月のビルボードライブ公演について、小西康陽が語る

10月に東京・大阪の〈ビルボードライブ〉で、ソロ・プロジェクトのPIZZICATO ONEとしてステージに立つ小西康陽。1984年に結成され、2001年まで活動したピチカート・ファイヴで「渋谷系」を牽引し、作詞・作曲・編曲・プロデュース、DJや文筆家としても活躍。11月にはピチカート・ファイヴの日本コロムビア時代の楽曲から小西康陽監修・選曲によるマニア垂涎の7インチ・ボックスと2枚組CD『THE BAND OF 20TH CENTURY:Nippon Columbia Years 1991-2001』がリリースされることがアナウンスされ、注目を集めている。
90年代を駆け抜けたピチカート・ファイヴの時代と、PIZZICATO ONEとして新たなステージに挑む小西氏に現在の心境を訊く。
「ピチカートってけっこうロックンロールだったんだな」
−−11月3日にリリースされるピチカート・ファイヴの7インチ・ボックス『THE BAND OF 20TH CENTURY:Nippon Columbia Years 1991-2001』がファンの間で話題になっていますね。
小西康陽:これは僕自身がピチカートの7インチが欲しいという理由だけでリリースされるようなものですね。巧妙なことに当時、7インチで発売された「ハッピー・サッド」(1994年)や「ベイビィ・ポータブル・ロック」(1996年)は今回のボックスには入っていないし、この曲は本当に自分が7インチとして欲しい曲を選びました。
−−日本コロムビア時代のピチカートがリリースしたシングルが必ずしも7インチになるわけではないところがポイントですね。
小西:そうなんですよ。アルバムは当時、ほとんどアナログ化されているんですけど、どうしても7インチでかけたいと思う曲をこの機会に。正直なことを言うと、これは僕さえ手に入ればいいんです(笑)。
−−小西さんも近年はDJでも7インチでプレイすることが多いですが、そうなったきっかけは?
小西:ちょうど10年くらい前、友だちとガレージ・ロックのパーティを始めたらDJみんなが7インチだったんですよ。2011年からスタートしたNOEL & GALLAGHERがそれに拍車をかけたところはありましたけどね。
−−あの息つく暇もなく選曲を繰り広げるお二人のDJスタイルは選曲も含めて非常に刺激的ですね。
小西:ありがとうございます。世間も7インチ・ブームになりましたけど、僕やNOELさんより以前に、MUROさんやDJ KOCOさんの影響の方が大きいと思うし、全体的にDJの高齢化が進んで、重いアナログを持ち歩きたくないという理由もあるかもしれないです。一晩中レコードを触っていられるDJは今もすごく楽しいですね。
−−そもそも、このタイミングで7インチ・ボックスとCDをリリースするのは?
小西:今回はそういう世間の流れとピチカート・ファイヴの日本コロムビアでのカタログ復刻がちょうど重なったという感じですね。たぶん、来年のオリンピックに向けて「東京は夜の七時」とかカタログに戻したかったんじゃないですかね?(笑)。
−−ピチカートの日本コロムビア・イヤーズの1991年~2001年は、ほぼ90年代と重なります。
小西:7インチにするにあたり、福富幸宏くんと作業していたんですが、ピチカートの曲は90年代のクラブ・ミュージックのエッセンスと昔ながらの伝統的な歌謡曲やポップスの要素が両方しっかりあって、短くエディットするのはけっこう難しかった。でも、1曲が無駄に長かったわけではなくて、それが90年代は必然的な長さだったということなんですよね。7インチは4分超えるといきなり音が悪くなっちゃうから、そこは苦心しました。
−−今回は7インチのためのニューエディットになるわけですね。
小西:そうです。長い曲は33回転で切ろうかと思って試しにやってみたら上手くいかなくて、無理してでも45回転にした方がやっぱり良かった。
−−そこで、あらためて発見したことはありますか?
小西:ピチカートってけっこうロックンロールだったんだなと思う曲があったのは嬉しかったですね。「エアプレイン」(『フリーダムのピチカート・ファイヴ』1996)なんて、パンクのオリジナル・シングルにも匹敵する音になりましたから。あと、「スウィート・ソウル・レヴュー」(1993)をあらためて聴いて、野宮真貴さんはこんなに素晴らしい歌手だったんだと思ったんですよ。あの頃の自分は曲作りやアレンジに夢中で目先のことしか見えていなかったんですが、レコーディング当時に高浪慶太郎さんが野宮さんの歌を絶賛していたのは覚えているんだけど、それが今頃になって分かった。
これは余談ですが、「スウィート・ソウル・レヴュー」はなぜかタイで大ヒットしたんですよ。Mr.Z(ソムキアット・アリヤチャイパーニット)がカヴァーして、オリジナルもラジオですごくかかっていたようで、不思議だったんですが、野宮さんの歌の上手さを再確認して、ここに秘密があったのかなと。アジア圏は歌の上手いヒトが好きですから。
−−「スウィート・ソウル・レヴュー」は、日本コロムビア時代の最初のシングルでもあり、CMのタイアップ曲として人気を博しましたね。
小西:そう。CBS・ソニー時代のシングルは「ラヴァーズ・ロック」(1990)だけだったし、日本コロムビアに移籍してからも1991年、1992年はシングルがないんですよ。タイアップの曲をつくるのは最初はすごく楽しかったんですけど、すぐ飽きちゃって(笑)。ずっと筒美京平さんのような作家になることに憧れていたんですが、自分には向いていないと分かりました。
−−今回、7インチ化される『SWEET PIZZICATO FIVE』(1992)収録の「万事快調」や「キャッチー」は、ピチカートが90年代に快進撃を続けてゆく予兆がありました。
小西:僕はずっと80年代の音楽が苦手だったんで、90年代になって良かったなという思いはありましたね。あの頃はホントに普通じゃないレベルでたくさんの曲をつくっていましたが、それは自分に余裕がなかったからだと思うんですよ。自分の音楽にもっと自信があったら、それほど多作にはならなかったんじゃないかな。でも、それも90年代の音楽の変化やスピードには合っていたような気がしますね。僕が尊敬する作家は、手塚治虫さん、湯村輝彦さん、信藤三雄さんなど、みんな多作なんですよ。
−−日本コロムビア時代はアルバム9枚、シングル21枚に加え、ミニアルバムやリミックスなど目まぐるしいほどリリースが続いていましたね。
小西:年に1枚のアルバムとそれに伴うコンサートをするのは契約の条件でしたが、リミックスや他の仕事を含めると契約以上の働きをしていましたね。今、冷静に分析すると、自分の貧乏性が出ていましたね。機会があれば少しでも曲をつくりたいと思っていたし、曲の評価は別として、それは今では出来ないことだからやっておいて良かったのかもしれないけど。
−−小西さんの作家性が確立された時期でもありましよね。
小西:そうですね。最近、DJをするとき自分でキラーな繋ぎだと思っているのが、シブがき隊「NAI・NAI 16」~シャネルズ(ラッツ&スター)「街角トワイライト」「ハリケーン」~郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」なんですよ。ハッと気がついたら全部、井上大輔さんの曲で、自分はその偉大さを見過ごしていたんです。若い頃って、あんまりものを知らないのに自分の価値観を決めてかかって、それで音楽をつくっていたところがあったなと思いましたね。あの頃、井上大輔さんや横浜銀蠅の魅力に気がついていたら、ピチカート・ファイヴも違う音楽性になっていたかな? とか(笑)。
−−渋谷系も違ったものになっていたかもしれない(笑)。
小西:ホントに(笑)。でも、まぁ、ピチカート・ファイヴも頑張っていたなとは思いますね。自分の中では必ずしも評価が高いわけではないんですが、ある時代、ある世代の音楽のひとつではあったと思います。
−−『THE BAND OF 20TH CENTURY』というタイトルにしたのは?
小西:2004年のソニー在籍時代の作品で構成されたアンソロジー『THE BAND OF 20TH CENTURY:Sony Music Years 1986−1990』や、日本コロムビアのDVDボックスもそのタイトルだったんで。ピチカート・ファイヴはやっぱり、20世紀の音楽だなと思うし、僕自身がどこまでも20世紀の人間なんですよ。
公演情報
【PIZZICATO ONE】
ビルボードライブ東京:2019/10/11(金)
1st Stage Open 17:30 Start 18:30 / 2nd Stage Open 20:30 Start 21:30
>>公演詳細はこちら
ビルボードライブ大阪:2019/10/15(火)
1st Stage Open 17:30 Start 18:30 / 2nd Stage Open 20:30 Start 21:30
>>公演詳細はこちら
リリース情報
『THE BAND OF 20TH CENTURY:
Nippon Columbia Years 1991-2001』
- ピチカート・ファイヴ
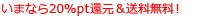
- 7inch BOX:
- 2019/11/3 RELEASE
- [COKA-70~85 定価:¥ 25,000(plus tax)]
- 16枚組(数量限定メンバー直筆サイン生写真封入)
- CD(2枚組):
- 2019/11/6 RELEASE
- [COCP-40957~8 定価:¥ 3,200(plus tax)]
- 詳細・購入はこちらから>>
※7inch BOXのみ早期予約特典としてボーナスディスクが付属。
収録曲:ベイビィ・ポータブル・ロック(宇宙組曲ヴァージョン)、東京は夜の七時(Studio Live)
予約対象期間:2019年7月31日(水)~8月31日(土)
関連リンク
Text:佐野郷子
「父親が僕が歌うアルバムを聴いてみたいと言っているので、その願いはかなえてあげたいかな」
−−小西さんがPIZZICATO ONEとして初のソロ・アルバム『11のとても悲しい歌』をリリースしたのが、ピチカート・ファイヴ解散からちょうど10年目の2011年でした。
小西:PIZZICATO ONEは自分からソロを出したいと言ったわけではなくて、向こうから来た話なんですよ。最初のアルバムは世界のヴォーカリストをフィーチャーした洋楽のカヴァー・アルバムという内容を考えたんですが、次の『わたくしの二十世紀』(2015)は、〈ビルボードライブ〉からライブのオファーを頂いたことがきっかけで、アルバムに発展したんです。
−−最初は小西さんの編曲でさまざまな歌手が〈ビルボードライブ〉のステージで歌う企画を打診されたとか?
小西:そうです。ライブのために一からアレンジするなら、レコーディングしたいと言って出来たのがあのアルバムでした。それでピチカート・ファイヴ時代のナンバーや僕が楽曲提供したセルフ・カヴァーを様々な歌手の方に歌っていただいて、僕自身が聴きたいアルバムにしようと。
−−2015年9月には〈ビルボードライブ東京〉で、アルバムに参加した甲田益也子さん、西寺郷太さん、ミズノマリさんらのヴォーカリストと共にPIZZICATO ONEとして初ライブを披露されました。
小西:あの時のステージは、ゲスト・ヴォーカリストが素晴らしい歌を披露してくださって、僕は楽器を弾くわけでもなく、「一体何をするんだろう?」と思っていた方も多かったと思いますが、4曲歌わせてもらいました。
−−この10月には4年ぶりのビルボードライブが控えていますが、どんなステージを考えていますか?
小西:今回、ゲスト・ヴォーカリストはいなくて、歌うのは僕です。去年、代官山でライブをやったときにはINO hidefumiさんにピアノを弾いてもらって6、7曲歌ったのですが、今回の編成はピアノ、Wベース、ギター、ドラムス、ヴィブラフォン。僕は楽器は弾かずに歌のみ。実は〈ビルボードライブ〉でライブ・アルバムをレコーディングしようと考えているんです。
−−それはおおいに楽しみですね。
小西:この編成は、僕の大好きなアメリカのシンガー・ソングライター、ティム・ハーディンのライブ盤『Tim Hardin 3 Live in Concert』(1968)と同じなんですよ。ライブ盤で自分の声を聴いてみたいというのと、そのアルバムの内ジャケットと同じような写真が撮りたいという理由も大きい(笑)。以前からヴィブラフォンを入れたライブは一度やってみたかったんです。
−−ライブ・レコーディングとなるとステージは緊張感ありそうですね。
小西:そうですね。でも、間違えてもライブだからと言い訳できるからいいかなと思って(笑)。最近はライブは映像が中心になってしまったけど、そこは20世紀の人間なので、できればアナログでも出したいですね。
−−4年前のステージではスクーターズに書きおろした「かなしいうわさ」(吉川智子とデュエット)、『わたくしの二十世紀』で小西さんが歌った「ゴンドラの歌」、ピチカート・ファイヴの「また恋におちてしまった」(『PIZZICATO FIVE』1999)と「子供たちの子供たちの子供たちへ」(『フリーダムのピチカート・ファイヴ』1996)を歌われましたが、今回は?
小西:ピチカートの古いレパートリーや、これまで提供した曲などを考えていますが、自分が歌う曲となると、やはり限られてくるんですよね。それこそ「スウィート・ソウル・レヴュー」みたいな曲は僕が歌っても似合わないですから(笑)。「また恋におちてしまった」は、ライブで自分が歌いやすいようにアレンジしてみたらすごくしっくりきたんですよ。あの曲の頃から作曲家とヴォーカリストの関係が微妙に変わってきたんだなと今度の7インチ・ボックスをつくって発見したことも面白かった。
−−その変遷も再確認できたと。
小西:野宮真貴さんという最高のヴォーカリストがいたから生まれた曲は多いし、それは感謝してもしきれないと思っています。野宮さんにはこれからも素晴らしい作曲家と出会って欲しいし、僕もまた誰かヴォーカリストと出会ったら、良い曲が出来るのかなという気持ちもどこかにあるんです。
−−その出会いにも期待したいですが、ご自身で歌うソロ・アルバムの予定は?
小西:いつかつくろうと思っていて、アルバム用に取ってある曲はあるんだけど、なかなか自分のための曲って書けないんですよ。人に当て書きするのが好きだったというのもありますけど、自分は難しいですね。そこでいつも筆が止まってしまう。でも、これ以上歳をとる前にとりあえず1枚つくっておきたいので、先ずはライブ盤を。いつかは全曲書き下ろしの自分が歌うアルバムが出せたらいいんですけどね。父親が僕が歌うアルバムを聴いてみたいと言っているので、その願いはかなえてあげたいかな。
−−ピチカート・ファイヴとしてデビューして34年。年齢とキャリアを重ねて、今、ソロで歌う心境は?
小西:20世紀は音楽は若い人のものだったと思うんですけど、今は色んな意味で変わりましたよね。パリによく行っていた頃、60年代に活躍していたアーティストがオリンピア劇場のような大きなホールでコンサートをしていて、「まだ現役でやっているんだな」と感じたけど、日本もそうなっていくのかなと思ったんですよね。昔は新作を出さないベテランのアーティストのライブは、「懐メロやってるんでしょ」と高を括っていたけど、レパートリーが若い時のヒット曲が大半だったとしても、それはそれで意義のあるものだと思うようになったし、若い時と聞こえ方が違って当然なんですよね。人は歳をとると変わることを身をもって感じています。
−−その時の年齢にふさわしい音楽のありかたを見せてゆくのは興味深いですね。
小西:そう。何年か前にジャズ・ミュージシャンのボブ・ドローが亡くなる前のライブを観たんですよ。若い時のレパートリーから最近の曲までやっていて、それがすごく面白かった。僕はコンサートには滅多に行かないんですけど、ああいう風になりたいなと思いましたね。10月の〈ビルボードライブ〉の僕のステージは、「小西の歌は隠し芸だからよかった」と言われないようにしたいです(笑)。

公演情報
【PIZZICATO ONE】
ビルボードライブ東京:2019/10/11(金)
1st Stage Open 17:30 Start 18:30 / 2nd Stage Open 20:30 Start 21:30
>>公演詳細はこちら
ビルボードライブ大阪:2019/10/15(火)
1st Stage Open 17:30 Start 18:30 / 2nd Stage Open 20:30 Start 21:30
>>公演詳細はこちら
リリース情報
『THE BAND OF 20TH CENTURY:
Nippon Columbia Years 1991-2001』
- ピチカート・ファイヴ
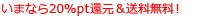
- 7inch BOX:
- 2019/11/3 RELEASE
- [COKA-70~85 定価:¥ 25,000(plus tax)]
- 16枚組(数量限定メンバー直筆サイン生写真封入)
- CD(2枚組):
- 2019/11/6 RELEASE
- [COCP-40957~8 定価:¥ 3,200(plus tax)]
- 詳細・購入はこちらから>>
※7inch BOXのみ早期予約特典としてボーナスディスクが付属。
収録曲:ベイビィ・ポータブル・ロック(宇宙組曲ヴァージョン)、東京は夜の七時(Studio Live)
予約対象期間:2019年7月31日(水)~8月31日(土)
関連リンク
Text:佐野郷子
関連商品




































